東日本大震災10年です。国会事故調査委員会関係の著作を紹介させて戴きました。
『黒川清氏(1950年生)と宇田左近氏(1956年生)は、2011年の福島第一原発事故に際して、『東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法 2011年10月7日法律第112号』に基づく調査を行い。所謂『国会事故調』報告書を作成した。 国外から事故を見ると、極言すれば『従来の日本でなされた、仕事の考え方そのものが事故の原因』で『組織を動かす責務を持った個人が最終責任(accountability)をはたしていない』としている。『2016.3.9 規制の虜 グループシンクが日本を滅ぼす』
 ●事故原因について、「規制当局は電気事業者の『虜(とりこ)』になっていた。その結果、原子力安全についての監視・監督機能が崩壊していたとみることができる」、この逆転現象は「規制(当局が被規制側)の虜= Reguratory Caputure 」とも呼ばれている。この遠因は、所属組織が変わらない単線路線のエリートに見られる「グループシンク(集団浅慮)」にある、としている。(page145)
●事故原因について、「規制当局は電気事業者の『虜(とりこ)』になっていた。その結果、原子力安全についての監視・監督機能が崩壊していたとみることができる」、この逆転現象は「規制(当局が被規制側)の虜= Reguratory Caputure 」とも呼ばれている。この遠因は、所属組織が変わらない単線路線のエリートに見られる「グループシンク(集団浅慮)」にある、としている。(page145)
●グループシンクに対する個人の主張の例として、1873年に福島で生れ日本人で初めて米国の大学教授のなった「朝回貫一」が日露戦争のさなかの1904年に、英語論文『日露紛争』において、日本の立場の国外アピールに成功するも、1909年には、当時の日本の「リーダー達」の周辺が、日露戦争後の政府の政策に異論を唱えず政府のやりかたに「服従」しているが、この「服従文化」が国を滅ぼすと予言し『日本の禍機 (講談社学術文庫)』を書いたとしている。(page221)
『2014.5.8 なぜ「異論」の出ない組織は間違うのか』
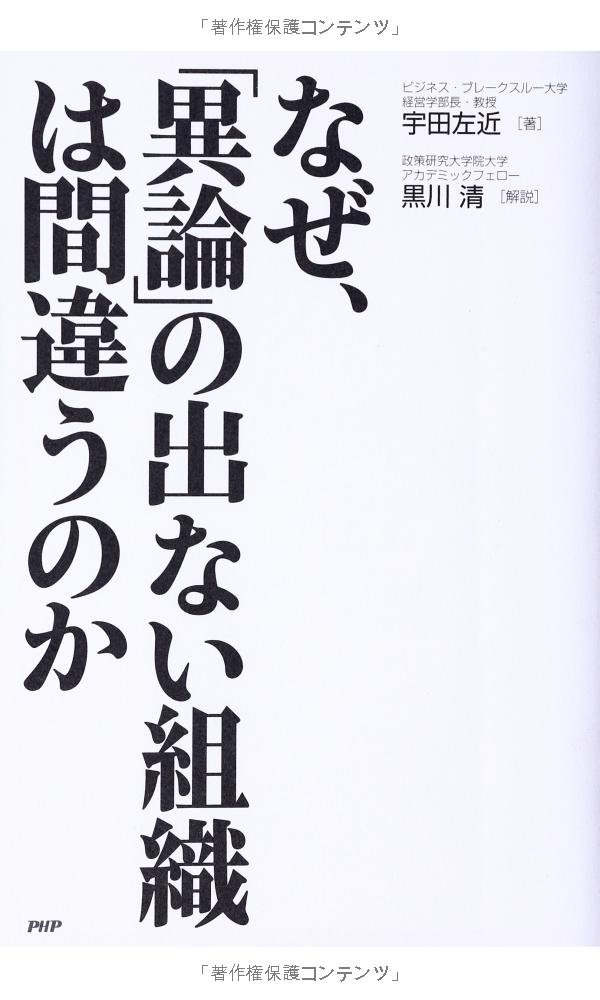 ●組織全体として外部の関与を阻み、前例踏襲を当然のこととし、内部合理性を好み、強烈な現状維持と既存組織の拡大、そしてそれを改革しようとする人に対しては面従腹背、不作為・先送りという手段で抵抗する姿は、不気味な「巨大生物」の様で、組織改革を行ってもそのDNAは新しい組織に移転されていく。このことは、それがより根深い個々人の「(集団思考型)マインドセット」に起因することを示唆している。(page98)
●組織全体として外部の関与を阻み、前例踏襲を当然のこととし、内部合理性を好み、強烈な現状維持と既存組織の拡大、そしてそれを改革しようとする人に対しては面従腹背、不作為・先送りという手段で抵抗する姿は、不気味な「巨大生物」の様で、組織改革を行ってもそのDNAは新しい組織に移転されていく。このことは、それがより根深い個々人の「(集団思考型)マインドセット」に起因することを示唆している。(page98)
●異論を唱えるためには同時に自らキャリアの選択肢を持ち続けることが重要だ。対抗が強く、社内志向の権力闘争に埋没する状況下でも、いざとなれば何とでもなる、という覚悟があれば、ただしいと思う方向にたいして堂々と意見を述べることも可能になる。この場合の選択肢を持つことは・・・あることに徹底することで、所属組織を超えた価値を身につけることが出来るということだ。最後は組織を離れ、職能を極めたプロフェッショナルとして社外、海外で活躍の道を求めればよ。外海は広いのだ。(page209)
『2013.03.16 S34卒50周年記念講演会・福島原発事故調査・検証を終えて・畑村洋太郎 』
が戸山高校において開催されました。講演の中で、 『電源喪失した暗黒の原発内で自分たちの自動車のバッテリーを担いでき て計器を読み取るなど、自己に付託 された使命を考え、主体的・能動的に行動した素晴しい人々の御蔭で今がある』とか 『事故発生直後に、オフサイトセンターから放射線量増を理由にセ ンター員が 避難したが、実はセンターの放射線防護の予算は3年前から確保されており総務 省が毎年防護実施の注意喚起をしたにも関わらず、実施しないと言う不作為があった』とか 『9.11米国の同時多発テロのあとで、米国から非常用発電機とコンプレッサー準備の必要性が機密保持のため口頭で助言されたが上部に伝達しない 傲慢があった』など、『各人一人ひとり、に付託された責任』を問ぅお考えが述べられました。
記念講演録音の一部書き起こし
『2013.04.13 特別対談 畑村洋太郎 vs 加藤陽子 福島原発事故から何を学ぶか 』
講演の中で●畑村:日本は「独立した個」をつくらないことを是として、最大効率で動くことばかり考えてきた。そのツケが今回まわってきたように思えます。
●加藤:これは近代日本の軍事史を研究している歴史家として、すごく既視感を覚えます。 たとえば、日米開戦を決意するにあたって、海軍のある動員課長が調べた「戦争になったら船舶が爆撃されてどのくらい失われるか」というデータが重要な意味を持ちました。彼は開戦派の上司に調べろと言われたから、撃沈数は少ないほうがいいんだろうと、わざと第一次世界大戦中の古いデータ、つまり航空機による爆撃のない時代のデータを調べて上に提出する。 その数字が御前会議でも使われて、結局、「撃沈される船舶量より建造できる船舶量のほうが多くなる」「ならば、開戦オーケー」という重大な決定につながりました。